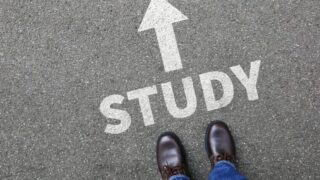今回は宅建に3ヶ月で最短合格するためのおすすめ勉強法について解説していきます。
- 期間3ヶ月で最短合格するために効率のいい勉強法
- 短期間で宅建に合格するためのおすすめ教材
- 宅建合格のために勉強時間を短縮させる方法
宅建に3ヶ月で最短合格するためのおすすめ勉強法【8つのステップでOK】

先に結論からお伝えすると、宅建に3ヶ月で最短合格するための勉強法は次のステップになります。
- 宅建に合格したい理由の明確化
- 宅建試験について理解する
- 分野別の目標点数を設定
- 自分にあった教材を選ぶ
- テキストを読み込む
- 過去問を解いてみる
- 予想問題集を解いてみる
- 間違えた問題の解説を読んで復習する
これらを1つずつ深掘りしていきます。
1.宅建に合格したい理由の明確化

まず最初のステップとして重要なのが、『なぜ宅建試験に合格したいのか?』を明確にすることです。
なぜなら試験勉強って初めこそはテンションをあげてできるんですが、1ヶ月2ヶ月と経ってくると次第にやる気が無くなってくるからです。
これまでの人生を思い返していただいてもそういった経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか?
しかし、こんな時でも動機が強ければ強いほど人は苦境に立ち向かうことができます。
なぜ合格したいのか紙に書いてみるのがオススメです
なんだ精神論か。と思う人もいるかもですが、勉強方法よりも実は一番大切なことなのでまずはご自身の目的を明確化することだったりします。
2.宅建試験について理解する

次にすることが宅建試験について理解することです。
勝負に勝つためにまずは相手を知ること、つまり宅建がどんな試験なのかということを把握することが重要です。
具体的には宅建試験の合格率や試験内容・試験日などについてはきちん把握できていますか?
もしまだ曖昧だなという方は宅建試験について以下の記事で網羅的にまとめているのでまずはそちらを読んでからこの記事に戻ってきてください。

3.分野別の目標点数を設定

3つ目にすることが分野別の目標点数を設定です。
宅建試験には大きく分けて以下の4つの分野が出題されます。
- 宅建業法
- 権利関係
- 法令上の制限
- 税その他
では分野別にどのくらいの得点を取ればいいのでしょうか?
この分野別の目標得点をしっかりと把握しておくことで、その分野にどのくらいの比率で時間を使えばいいのかが分かってきます。
※以下は実際に私が目標としていた分野別の得点になるので参考にしてみてください。
宅建業法
目標得点:18点/20点
この宅建業法は一番の得点源になる分野です。内容も難しくないので、暗記さえすれば確実に得点が取れます。
数問はひっかけのようなパターンも存在しますが、基本を押さえておけばどんな問題がひっかけなのかが分かってくるようになるので問題数をこなすことが重要ですね。
この宅建業法が宅建試験の合否を分ける最大のポイントです。ここで正直満点を取れたらかなり高い確率で合格することができるはずです。
権利関係
目標得点:10点/14点
宅建の試験の中で一番難しい分野です。民法や借地借家法など法律に関する問題が出題されるので、かなり範囲も広く対策が取りにくいです。
そのため目標点数も14点中10点取れれば十分です。(最低でも8点は取りたいですね。。)
権利関係に勉強時間を取るよりも他の宅建業法や法令上の制限などの暗記科目に時間を当てることをオススメします。
法令上の制限
目標得点:6点/8点
こちらも宅建行法と同じく暗記科目なのですが、「国土利用計画法」「農地法」「建築基準法」など覚える内容がとにかく多いです。
なので苦手意識を持つ人も多い分野かと。
わたし自身も法令上の制限の分野は苦手で苦労したんですが、時間をかけていくうちに全体像が見えてきて得点も上がっていきました。
最初はとっつきにくい分野ですが、慣れれば宅建業法と並んで得点分野になりえます。
税その他
目標得点:6点/8点
「税金」や「住宅金融支援機構・景品表示法・統計」など範囲は広いように感じますが、出題されているポイントは決まっているので得点は取りやすい分野です。
過去問を解いていくとだいたいどんな問題が出るのかが掴めてきます。
合計点数は40点と厳しめに設定しておく。
目標通りに分野別の得点を取れれば、40点になります。
年々宅建の合格点数は上がってきている傾向にあるのですが、40点取れれば確実に合格できます。(合格点が40点を超えた年はこれまでありません。)
もちろん試験によって簡単だった分野、難しかった分野があるので目標通りの点数を取るのは難しいとは思いますがあくまで目標として意識しておくことが大切です。
4.自分にあった教材を選ぶ

さて4つ目のステップでは実際にこれから学習していく教材を選びましょう。
圧倒的におすすめなのが通信講座になります。
なぜなら通信講座は通学スクールよりも割安で、かつ合格までのカリキュラムがしっかりとしているので独学よりも遥かに効率よく学習ができるからです。
お金をケチって独学で何度も試験に落ちるより、通信講座を使って1回目の受験でスパッと合格した方が結果的に私たちにとって一番大切な時間を失わなくてすみます。
どういった通信講座がおすすめなのかは別の記事にまとめているのでぜひそちらを参考にご自身にあった通信講座を選んでみてください。

5.テキストを読み込む

さて、ようやく実際の学習ステップに入ります。
まずは選んだ通信講座についている基本テキストを読み込みましょう。最低3周は読んでください。(時間があれば5周以上)
不思議なもので何周か読み込んでいるうちに少しずつ理解できてくるのが実感できるはずです。
しんどいとは思いますがこれが最初の難関です。頑張って乗り越えましょう。
6.過去問を解いてみる

テキストの読み込みが最低でも3周以上できたら、次は過去問を解いていきましょう。
テキストを3周読めばある程度知識が入っているはずです。ここからはアウトプット型の学習を進めていきます。
最初はわからなくて当然です。問題をたくさん解いていくうちに必ず似たような問題に出会います。
そうしていくうちに宅建試験の出題傾向が見えてくるはずです。
過去問は何年分解けば良いのか?
過去問を解けば解くほど問題の出題パターンが見えてきます。とにかく繰り返し解くことで過去問を8割以上は正解できるという状態にしておきましょう。
また通信講座の場合には過去問集のテキストがついていると思いますが、解説の部分が非常に丁寧に書かれているので間違えた問題は必ず解説を読むようにしましょう。
7.予想問題集を解いてみる

過去問10年間を2周ほど終えたら、次は予想問題集を解きまくりましょう。
過去問ばかりを解いていると問題に慣れてきてしまいます。そのレベルまで達するといつまでも過去問で同じ問題を解いていても意味がありません。
次は初めて見る問題ばかりが出題される市販模試をどんどん解いていく必要があります。
※通信講座なら過去問とは別に問題集がついているのでそれを解いていけばOKです。
8.間違えた問題の解説を読んで復習する

これはかなり重要なステップです。
問題を解いた後に間違えた問題は必ず解説を読んで復習しましょう。
よく問題をたくさん解いて終わりという人がいますが、それだと効率が悪いです。野球で例えるなら、ただ何も考えずにバットを振っているのと同じです。
何がダメだったのか?自分は何ができていないのか?それを見直す作業が上達には必ず必要です。
問題→解説→テキストを繰り返す
この3つのステップを繰り返していくことによって、苦手な分野が段々となくなってきます。
そして間違えた問題についてテキストで確認することによって何倍もの効果で内容を理解することができます。
私は間違えた問題をノートにまとめていました。そうすることで直前期に自分の苦手な問題のみを見直すことができるのでおすすめです。
1〜8のステップをとにかく繰り返せば本番で40点以上狙える。

ここまで説明してきた1〜8のステップを踏めば本番で40点以上の得点を十分狙うことができます。
基礎→演習→復習→記憶に定着という流れを繰り返すことで確実に得点が上がるからです。
特にステップ5〜8は時間があるかぎり繰り返してください。
そうすることで自分の苦手な問題がどんどん無くなってきて、試験直前には全てやり切ったという思いで本番に臨むことができるはずです。
宅建に3ヶ月で合格するために必要な勉強時間は?

宅建に合格するには一般的には300〜500時間必要だと言われています。
もちろん人によってこの必要時間は差がありますが、今までの合格者にお話を聞いて平均して300時間くらいははみなさん勉強されていました。
- 1日1時間毎日勉強したとすると300日
- 毎日2時間ずつであれば150日
- 毎日3時間ずつであれば100日
とは言え、なかなか社会人の人にとって1日3時間の勉強時間を確保するのは難しいですよね。なので時間にとらわれ過ぎずにしっかりと密度のある勉強をするようにしましょう。
ただ何も考えずに3時間学習をするよりも、トライアンドエラーを繰り返しながら考えつつ勉強していく2時間の方が当たり前ですが有効的です。
また独学の場合と通信講座を使った場合でもこのあたりの合格に必要な勉強時間も大きく変わってきます。
どの通信講座がおすすめかは下の記事で紹介しているので、最適な通信講座を選んでガッツリと勉強時間を短縮化させてください。



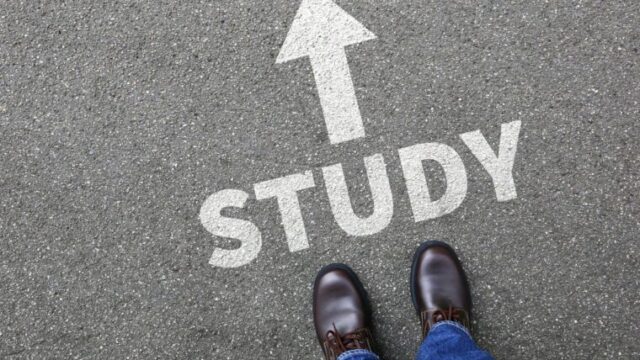


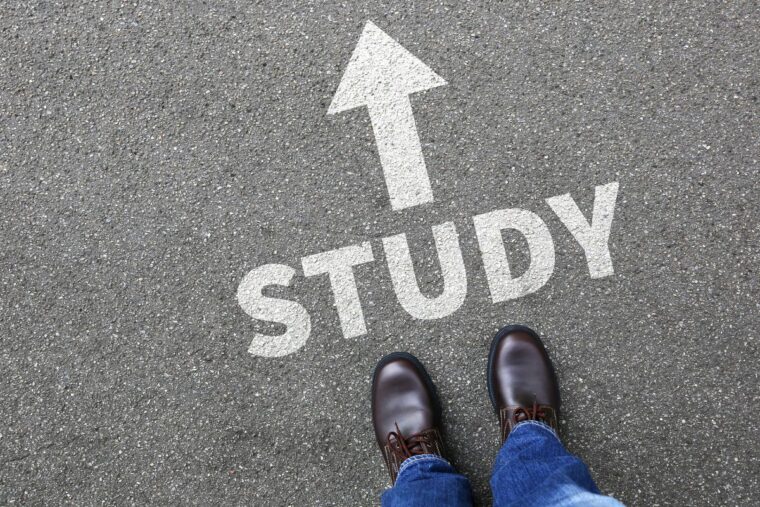




 フォーサイト
フォーサイト 
 アガルート
アガルート 
 スタディング
スタディング