今回は宅建で過去問を使ったおすすめの勉強方法について解説します。
- 過去問を使った勉強方法
- 宅建の過去問は何年分解けば良いのか?
- 宅建は過去問だけで合格することはできるのか?
宅建で過去問を使ったおすすめの勉強方法
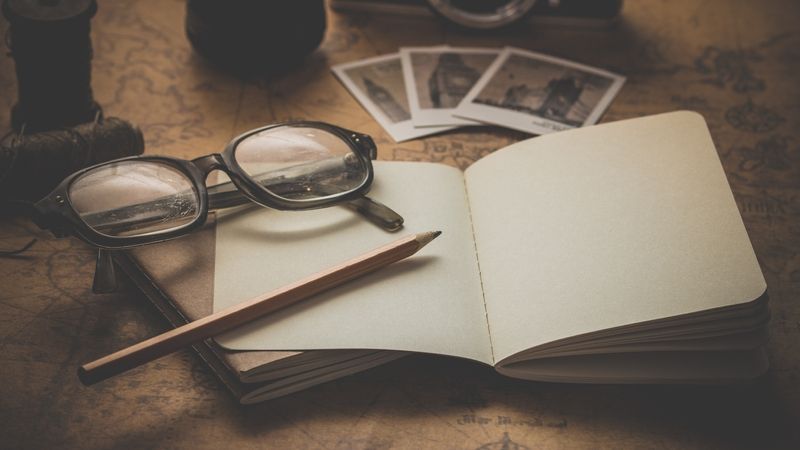
宅建で過去問を使った勉強法は次の5つのステップがお勧めです。
- 過去問をまずは解いてみる
- 分からなかった問題の解説を読み込む
- 間違えた問題にはチェックを入れておく
- 過去問で分からなかった部分を基本テキストで振り返る
- 1~4のステップを繰り返す
これらをそれぞれ1つずつ深掘りしていきます。
過去問をまずは解いてみる

基本テキストを読み終えたら、まずは過去問を解き始めましょう。
そうすることで後から見直しをする時に、自分が完全に分かっている問題を省いて効率的に復習をすることができます。
もちろん、最初の間は分からない問題だらけだと思います。私も最初は分からない問題だらけでかなり萎えましたが、段々と理解が深まっていき、最後のあたりはほとんどチェックマークをつけなくていいくらいになっていました。
分からなかった問題の解説を読み込む

過去問を解き終えたら、次は解説を読み込みましょう。
過去問のテキストを購入している方であれば解説書も一緒についていると思いますが、ネットでダウンロードした過去問を解いた方であれば『宅建高速塾』がおすすめです。
『宅建高速塾』は無料とは思えないほど丁寧に過去問を解説してくれているので、私も現役時代は本当にお世話になりました。
特に分からなかった問題や、悩んだ問題は、なぜ?を意識して解説を読むようにしましょう。
間違えた問題にはチェックを入れておく
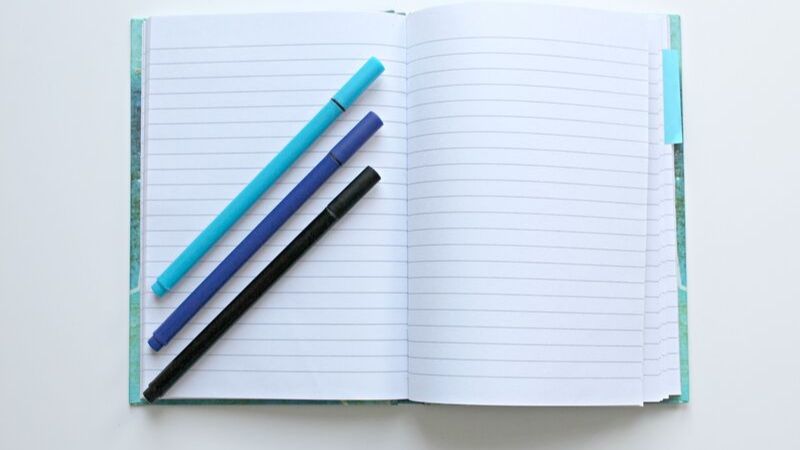
過去問を解く→解説を読むを終えたら、今回間違えた問題を二度と間違えないようにチェックをしておきましょう。
方法はノートにその問題を残しておきでも良いですし、問題用紙の余白にチェックマークを入れるでも構いません。
とにかく次回同じ問題を解く時にそれと同じ問題を間違わないようにする!この意識を持つだけでもかなり変わってくるはずです。
過去問で分からなかった部分を基本テキストで振り返る
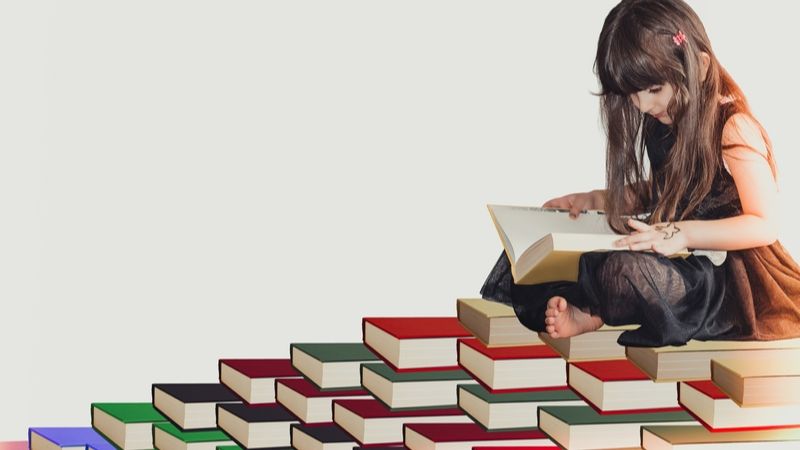
これはめちゃくちゃ重要です。
分からなかった問題が過去問を解いてみてあったはずなので、その分野のテキストに振り返りましょう。
アウトプット→インプット→アウトプットを繰り返すことがとにかく大切です。分からなかった問題を基本テキストで振り返ることで知識をどんどん定着させましょう。
1~4のステップを繰り返す
後はシンプルに1~4を繰り返しましょう。
これを続けることによって最初は分からなかった過去問が次第にスラスラと解けるようになってくるはずです。
宅建の得点をあげるためにとにかく重要なのが、繰り返すことです。反復練習です。
過去問を解いてみて、分からないことがあれば解説を読んで、基本テキストに振り返るこれを繰り返せばかなりレベルアップできるのでぜひ挑戦してみてください。
宅建の過去問は何年分解けば良いのか?
こういった疑問を持つ方もいると思います。
結論として過去問は10年分解くようにしましょう。さらにできれば2周以上しましょう。なぜなら1度解いただけでは、すぐに忘れてしまうからです。
ただ時間がなくてそんなにもできない…という方は過去5年分を2周以上解くようにしましょう。10年分を1周分だけ解くよりもその方が効率的です。
点数が取れないならとにかく繰り返して9割以上は取れるようになるのが望ましい…!
 最初はなかなか点数が取れず悩むことがあるかも知れません。
最初はなかなか点数が取れず悩むことがあるかも知れません。
私自身も過去問を解き始めた時は9点くらいしか取れなくて絶望に陥ったことがあります。
ただ回数をこなしていくうちに過去問のパターンに慣れてきて点数が取れるようになってきます。
何周しても良いので、本試験までに過去問を9割以上は解けるようにしておくことが望ましいです。
宅建は過去問だけで合格することはできるのか?

結論としては過去問だけで合格はできますが、正直難易度は高めです。
なぜなら宅建は7割以上過去問から出題されると言われていますが、年々過去問からの出題数が減ってきているからです。
もちろん過去問は重要な勉強の一つなのですが、それだけだと確実に合格を目指すことは難しくなっているのです。
ではどういった勉強方法なら合格の可能性を上げることができるのかについては下の記事に詳しくまとめているので気になる方は参考にしてみてくださいね。
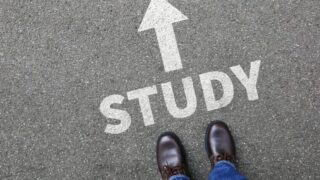


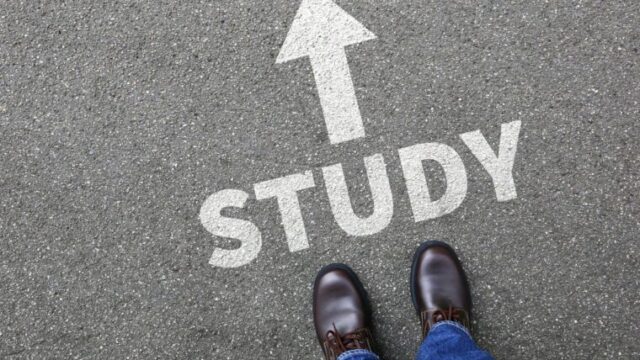





 フォーサイト
フォーサイト 
 アガルート
アガルート 
 スタディング
スタディング 






