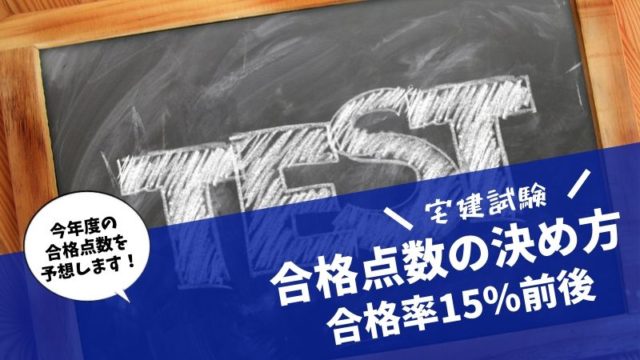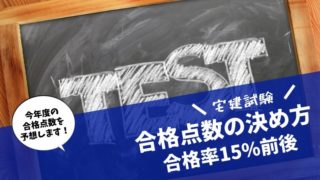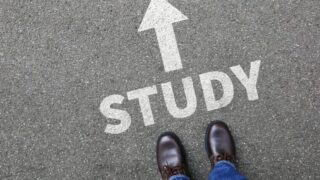宅建の権利関係・民法のおすすめ勉強法!攻略のポイントやコツについて取り上げていきます。
- 宅建の権利関係・民法のおすすめ勉強方法
- 宅建の権利関係・民法で得点UPするコツや攻略法
- 権利関係・民法を勉強するのにおすすめの教材
宅建の権利関係・民法のおすすめ勉強方法

結論としては権利関係は次の4つのステップで学習をしていくのがおすすめです。
- テキストを読んで権利関係の大枠を掴む
- 過去問を解いて権利関係の出題パターンを把握する
- 過去問を解いて苦手だった分野をテキストで学習する
- 新しい問題を解いて色んなパターンに慣れる
これらを1つずつ解説していきます。
テキストを読んで権利関係の大枠を掴む
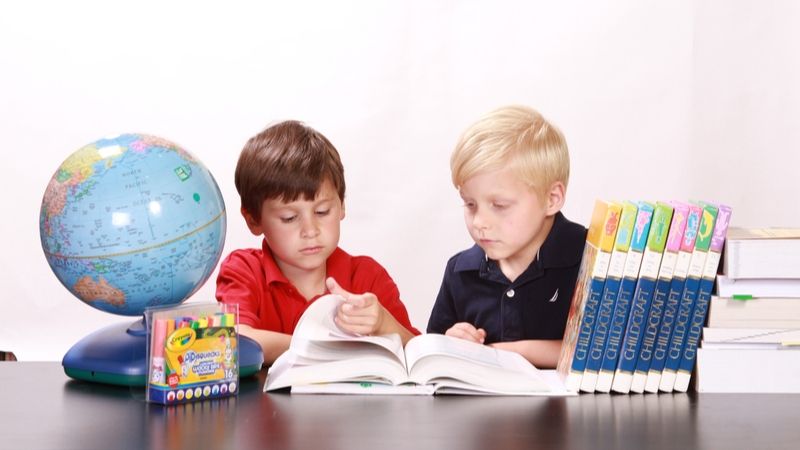
まずは何も分からないと思うので基本テキストを最低でも3周は読み込みましょう。
最初は全く分からなくてもとにかく先に進むことを意識してみてください。後から振り返るとすんなりと理解できたということがよくあります。
とにかく挫折せずに続けることが大切です。
過去問を解いて権利関係の出題パターンを把握する

テキストを3周読むことができたら次は過去問を解いていきましょう。おそらく最初は全く解けないはずです。
この段階で過去問を解けるようになる必要はありません。まずはどんな風に権利関係の問題が出題されているのかを把握することが大切です。
ある程度過去問を解いているとよく出題されるパターンや分野が見えてくるはずです。
過去問を解いて苦手だった分野をテキストで学習する

過去問を解いて自分の苦手分野やよく出題される分野が分かったらもう一度テキストに立ち返りましょう。
過去問を解いてからテキストに振り返ると最初の頃よりも情報が頭に入ってくるのを感じることができるはずです。
インプット→アウトプット→インプットを繰り返すことで知識はどんどん定着していきます。
新しい問題を解いて色んなパターンに慣れる

ある程度基本テキストと過去問での学習が進んできたら次は予想問題集などを解いていきましょう。
予想問題集ではこれまで見たことのない新しい問題が出題されています。初めて見る問題を解いておくことで本番試験までに様々なパターンに慣れておくことが目的です。
私自身も過去問を解いた時点でかなり自信がついていたのですが、予想問題集になると全く解けませんでした。
過去問だけではなく、予想問題集を解くことによって一気に宅建の知識を身につけることができるのでおすすめです。
宅建試験の権利関係は何問中何点取れば良い?

宅建試験で権利関係・民法の分野は全部で14問出題されます。
最低でも半分の7点は取りたいところですが、理想は10点目安になります。
それぞれの問題番号でどういった問題が出題されるかは以下にまとめました。
民法 [1問目〜10問目]
代理、請負、債権・債務、抵当権など、宅建業で関係のある部分に限られています。
ただ単に条例を覚えるだけでなく、「条例を覚えた上で考えて解く」といった能力が求められます。
暗記+応用のイメージです。
借地借家法 [11問目〜12問目]
借地関係、借地権の存続期間と更新、借地権の対抗力、定期借地権など
地主と借地人の権利・義務を定めた法律で、更新の期間や催告の期間等の数字がよく出てくる分野です。
数字を暗記しなければ解けませんが、逆に暗記することで簡単に選択肢から答えを選び抜くこともできます。
不動産登記法 [13問目]
家権の存続期間と更新・解約の申入れ、同居者・転借人の保護、定期建物賃貸借など
不動産の登記に関する法律で、民法ほど難しくなく試験問題は1問と少ないのでぜひ取りたい問題でもあります。
建物区分所有法 [14問目]
専有部分と共用部分、区分所有者と管理者の役割、規約・集会による管理の仕組みなど
マンション等の専有部分、共用部分の権利などに関する法律で、不動産登記法と同じく例年1問ほど出題されます。
権利関係の中では一番簡単な科目なので必ず取りたい1問です。
宅建の権利関係・民法の攻略法やコツについて

宅建の権利関係を勉強するときにはいくつかコツがあります。このコツを理解しておくだけでも権利関係の得点をあげることができます。
宅建の権利関係を勉強するときのコツは次の4つです。
- 民法はなぜ存在するのかを理解する
- 善人が誰で、悪人が誰なのか?を意識する
- 誰と誰が争っているのかを理解する
- 原則と例外を意識する
それぞれについて1つずつ深ぼって解説していきます。
そもそも民法とはなぜ存在するのかを理解する

そもそもなぜ民法は存在するのでしょうか?
しっかりとしたルール(民法)を決めておかないと善人が泣いて悪い人が常に笑う国になってしまいますよね。
当たり前のようですが、この『民法は善人を守るためにある』という前提を理解しておくだけでも解ける問題があります。
善人が誰で、悪人が誰なのか?を意識する

宅建の権利関係の問題を解くときには善人が誰で、悪人が誰なのかを正確に理解するようにしましょう。
例えば問題文を読んだ時にABCという3者が出てきたとします。
この中で誰が善人で保護される立場の人なんだろう?誰が悪い立場の人なんだろう?と考える癖をまずつけましょう。実生活に当てはめてみるのもかなり効果的です。
そうすることで、これは多分この人を守ってあげないといけないだろうなという感じに答えが見つかってきます。
誰と誰が争っているのかを理解する

上記で『誰が保護されるべきなのか』を意識することと言ってきましたが、それを理解するために大事なのが『今は誰と誰が争っているのか』ということを知ることです。
民法の問題は文章がダラダラ並んでいて、結局なにが言いたいの?ってなってしまうことがよくあります。
なので文章ではなく、必ず図形で理解するようにしましょう。
図にすると分かりやすい

例えば、双方代理のケースであれば上記のような図にしてみると分かりやすいです。簡単で全然構いません。
こうすることでイメージがかなりしやすくなるはずです。ダラダラと書かれていた文も図形にすることで一瞬で理解できます。
慣れてくると頭の中でこの図が描けるようになってくるのですが、慣れるまではきちんと一題ずつ図形を書くようにしましょう。
原則と例外を意識する

何事もそうですが世の中には例外というものが存在します。
民法にももちろんこの例外が存在します。それが但し書きというものです。
例えば民法116条で考えてみましょう。
民法第116条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
ただし、第三者の権利を害することはできない』の部分が例外に当たります。そして問題はこの例外のパターンを出題してくることが多いです。
この条文だと原則と例外は次のようになります。
- 原則:追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
- 例外:第三者の権利を害することはできない。
こういう風にどんな時に例外が発生するのかを理解しておくことで権利関係の得点はかなり上がってきます。
権利関係の得点をUPできるおすすめの教材

ここまで宅建の権利関係・民法の勉強法やコツについて解説してきましたが、学習をより効率的に進める上で大切なのが教材です。
教材選びを間違えてしまうと権利関係が理解できずに試験に落ちてしまうリスクが上がります。
フォーサイトはとにかくテキストの解説がフルカラーで分かりやすく、問題集も充実しているので権利関係の得点を一気に上げることができます。
フォーサイトについて詳しくは下の記事にまとめているので、権利関係の得点をもっとUPさせたいという方は参考にしてみてください。



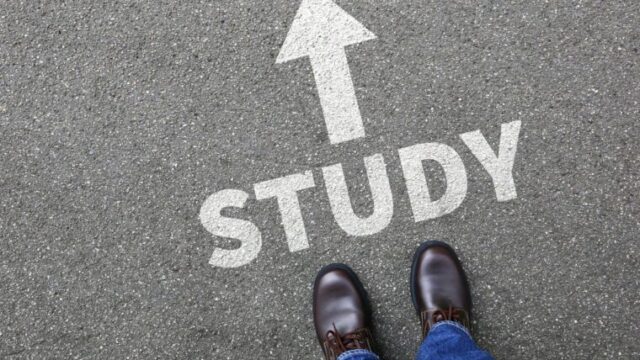






 フォーサイト
フォーサイト 
 アガルート
アガルート 
 スタディング
スタディング